Pioneers
先駆者インタビュー
- Pioneer (02)
- R&D統括部
AI技術部 - 中村 紘人
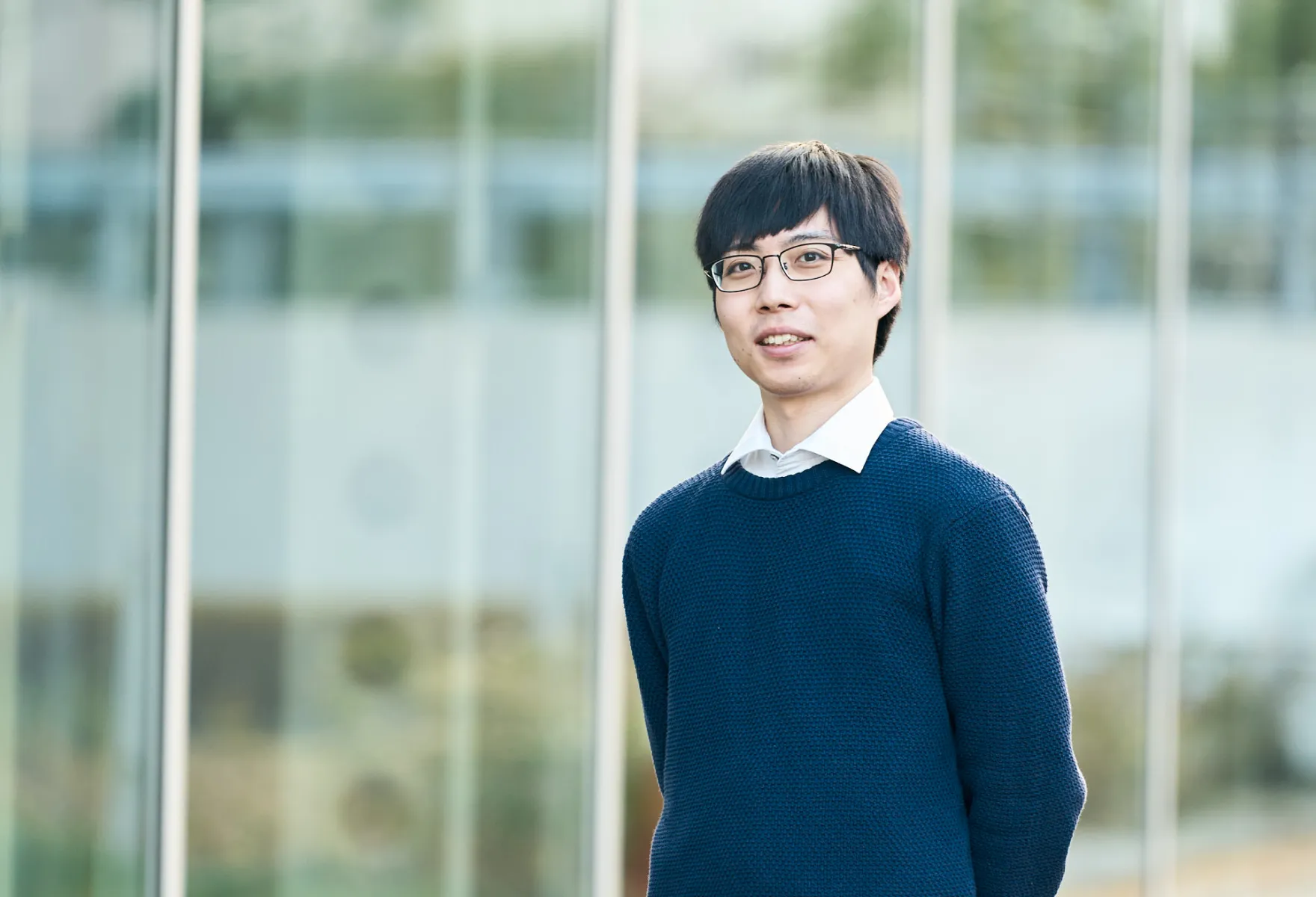
カーナビAIに踏み込み、
世界中で使われるモデルを作りたい。
研究の先に待っているのは、カーナビと会話できる未来
R&D統括部の「AI技術部」に所属しています。AI技術部は約2年前に新設されたパイオニアの中でも新しい部署で、AIとモビリティを掛け合わせた新しい移動体験をつくるためのさまざまな開発を行っています。私が担当しているのは音声認識です。バイク用の音声ナビゲーションアプリ「MOTTO GO(モットゴー)」に搭載されている音声認識AIを作っています。
たとえば「コンビニに寄りたいから、コンビニ経由の帰宅ルートを教えて」とナビに話しかけたら、画面と音声でルートを案内してくれる。バイクの移動体験を快適で安全なものにするため日々実験と検証を繰り返しています。
しかし、音声認識×バイクには、とても高いハードルがあります。まず、バイクは運転手がむき出しの状態なので外音がとても大きいんです。そのため、ノイズに強い耐性を持った音声認識AIにしなくてはいけません。現在この機能は、試験運用としてリリースしている状態ですが、まだ改良の余地は大いにあります。

厳しい意見こそ、重要なフィードバック
体験設計は改善できるから面白い
ユーザーからのレビューで厳しい意見をいただくこともあります。走行中に内容を聞き間違えてしまったり、処理に時間がかかりすぎたり、まだまだ課題は山積みです。でも、そこから改善していけるのが「コトづくり」の面白さだと思います。「モノづくり」は仕様変更のハードルが高いのですが、MOTTO GOはサービスとして提供しているので、アップデート前提ということもあり、厳しい意見は改善するための重要なフィードバックなんです。
ユーザーの意見から見逃していた課題が浮かび上がってくることもあります。例えば、社内でテストした通話マイク以外にも、ライダーの間ではいろんな機種のマイクが使われていて、マイクの相性次第ではうまく認識されないことがあると、ユーザーレビューから気づかされました。
このように、ユーザーから集まった声や使用ログをもとに体験価値を高めていく過程は、非常にやりがいを感じます。モノづくりで培ったパイオニアのスピリットがコトづくりに活かされ、技術面だけでなく体験面でもパイオニアの凄みが伝わっていく未来を想像すると、ワクワクしますね。

ものづくりとIT
興味の交差点にパイオニアがあった
パイオニアへの入社を決めたのは、モノづくりとコトづくりの両方を自社で行なっているところに惹かれたからです。大学時代、物質・材料関連の研究をしていたのですが、新しい性能を持った新種の物質を作り、その性能を測定し、数値の要因を分析して改善していくという実験プロセスがとても自分に合っていたし、好きでした。
私は3歳の頃に初めてPCを触り、小学生からLinuxを使っていたくらいIT分野も好きだったので、インターンではテック系スタートアップやベンチャー企業に参加していました。今思えば、ユーザーに近いところでコトづくりができるのが好きだったんだと思います。
そして就活期。モノづくりとIT、両方楽しめる会社はないだろうかと探していたときに出会ったのがパイオニアでした。就職活動をしている皆さんに伝えたいのは「自分が楽しめると思うところに、ぜひこだわって欲しい」ということです。楽しいとか、ずっとやっていられるというのは、ある種の才能だと思います。私はそれがモノづくりとITでしたが、これは人によって違うはず。ぜひ、自分の心にある「楽しそう」の種を見逃さないようにしてほしいです。

MY DREAM
世界中で使われるような、AIモデルを作りたい
ずっと手を動かし続けるエンジニアでありたいと思っています。というのも、自分は今の開発領域が好きなんです。自分の作ったものが機械に搭載されて、それがユーザーに利用される。そして今後は、自分の携わったAIモデルがユーザー体験の質を大きく左右する。その大元となる部分を作れるという仕事に今はとても魅力を感じています。
今後もAIの質をどれだけ高められるか、というところにチャレンジし続けていきたいです。いずれは世界中で使われるようなAIモデルへ。群雄割拠の領域ではありますが、だからこそ燃えますね。そのモデルだけで論文が出せたり、特定のスコアで世界一位を取ったりできるようなAIモデルを作ってみたいです。



